
NHKの「あしたが変わるトリセツショー」で、スマホとのつきあい方が紹介されていました。
”スマホが人体に与える影響”の研究は、世界中で進んでいるようです。毎日の生活にスマホは必要なものになってきているので、興味をそそられる内容でした。番組の内容をまとめてみました。
- スマホ依存と感じている方
- スマホ時間を減らしたい方
- スマホとの上手なつきあい方を知りたい方
睡眠前のスマホについて
睡眠学者の柳沢正史氏が登場!
柳沢氏は、株睡眠障害を効果的に予防・診断する筑波大学発スタートアップ企業「株式会社S’UIMIN」の取締役CSO会長もやっていらっしゃるそうです。
スマホの睡眠への影響は、使い方により入眠をスムーズにするそうです。
光
スマホには、光の自動調節機能があり、夜になると画面の明るさが暗くなっていきます。

その機能を切っていなければ、光の強さ自体は、とても弱いそうです。
- それほど気にしなくていい
- 近づけすぎに注意
実際に、柳沢先生がベッドでスマホを見る入眠ルーティーンが映されましたが、部屋は真っ暗な状態でした。部屋の電気をつけていても、同じ効果があるのか、ちょっと疑問が残りました。
コンテンツ
自分がリラックスできるコンテンツ動画などを短時間見るのは、入眠ルーティーンになるそうです。
ゲーム・SNS・メッセージ送信・ショート動画などはお勧めできないそうです。
- イヤなことを忘れられるものを選ぶ
- 操作を伴うものは注意

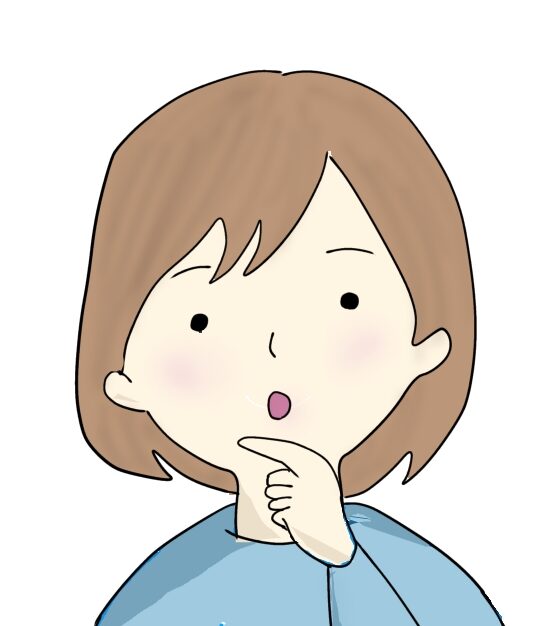
コンテンツ選びが大事なんだね
スマホ時間の減らし方
ドイツ発最新メソッド
近年の”スマホが脳に与える影響”の研究で、依存が進むと集中力・記憶力が減りうつ状態になる場合もあることがわかってきたそうです。
ドイツルール大学ボーフム精神衛生研究治療センター准教授のユリヤ・ブライロフスカヤ氏は、15年にわたりデジタル技術が真理に与える影響を研究されています。
彼女が600人を3つのグループに分けて行った実験は、スマホ時間を減らすヒントになるものでした。
1、スマホを通常通り使用するグループ
2、スマホ未使用のグループ
3、スマホ使用時間を1時間減らすグループ
1週間だけ、これを実行してもらったそうです。その後、普通の生活をし、1ヶ月後・4ヶ月後にデータを取った結果・・・

3の1時間だけスマホの使用時間を減らしたグループが、その後の生活でも使用時間が一番少なかったそうです。
1週間、スマホの使用時間を1時間減らす。
そして、使用時間が減っただけでなく、生活の満足度が上がり、不安感が減るという結果が出たそう。
- 仕事のモチベーションup↑
- 生活の満足度up↑
- 運動量up↑
- 喫煙本数の減少↓
スマホは、今や生活の重要な一部だから、”スマホ断ち”は現実的ではないし、短期間我慢できたとしても、その後逆に使用量が増える結果になったそうです。
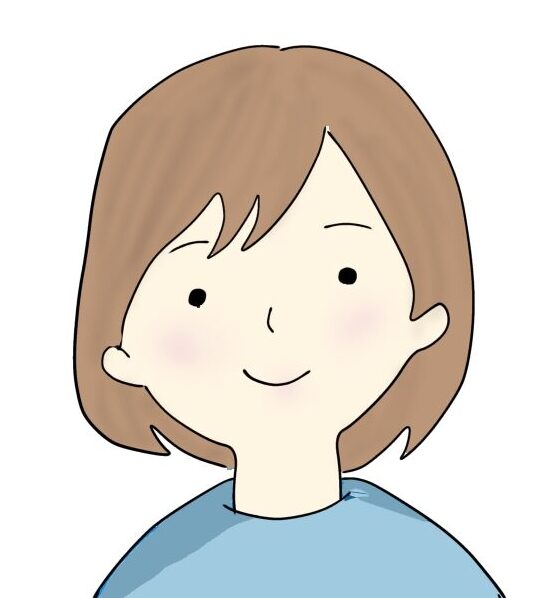
確かに、生活の色々な場面で、スマホは必要です〜
番組では、実際に「トリセツチャレンジ」として、数人の視聴者に実験していました。
1時間減らす、という取り組み易さが成功を招いたようです。まーテレビに映るっていうのもかなりモチベーションになったはずですが。実際にスクリーンタイムが減ることで、皆さんが感じていたのが達成感!自分にも出来た!という成功体験が、継続の力になっていくのだと思います。

ネット依存外来オススメの方法
ネット依存外来の治徳大介先生が紹介されていたのは、こちら。
- 手元からスマホを離す
- 手の届かないところに置く
- モノクロにする
- 設定をグレースケールにすると、スマホ時間が減るという海外の研究結果あり
- 仕事とプライベートなどで、ホーム画面を分ける
- ひと手間かかることで、抑制になる
ひとつひとつは割と些細なことなので、大変さを感じず、達成感を得ることができるそうです。
これが「自己効力感」(特定の課題や目標を達成するために「自分にはできる」と信じる気持ちや認知。)となり、スマホ依存の予防になるそうです。
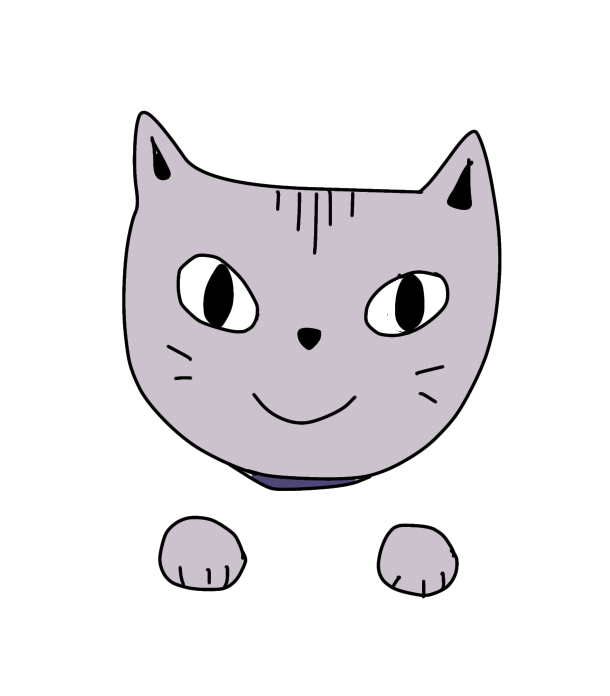
自己効力感!
おわりに
私が嫌なのは、スマホでSNSなどをダラダラと長時間見てしまった後の、虚しさ。ああ、時間を無駄にしてしまったと罪悪感を持ったり、人を羨ましく思い劣等感を感じたりと、マイナスの感情が押し寄せます。
そういうところが、心のために良くないことなんでしょうね、きっと。
スマホの使用時間を減らして、自己効力感を高めなくては。
と、この番組がきっかけになり、以前読んだ「スマホ脳」という本を思い出し、読み返してみました。
デジタル技術が私たちの心身に与える影響は、これからもっと解明されていくと思います。新しい情報を取り入れつつ、上手に使って、スマホに振り回されないようにしていきたいですね。
読んでいただきありがとうございました。



